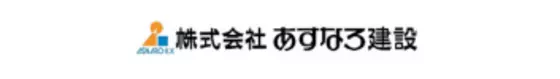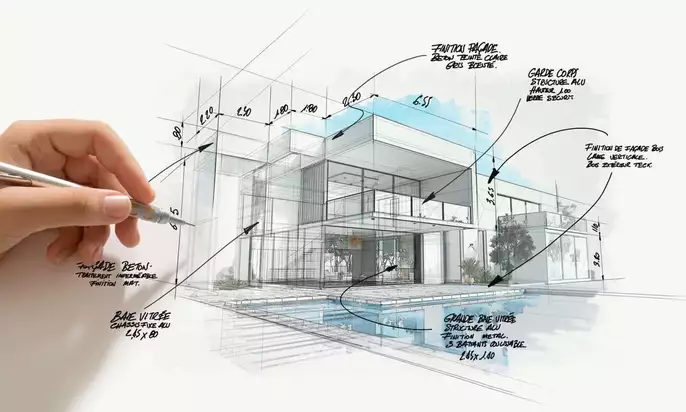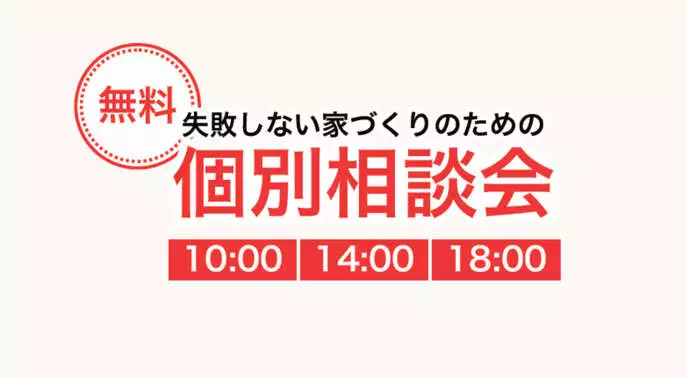住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、住宅ローンの支払いで支払った利息を、課税所得から差し引くことができる税制優遇措置のことを言います。
つまり、住宅ローンで支払った利息の一部が国から還付されるという制度のことです。
この住宅ローン控除制度を利用すれば、最大400万円以上の還付を受けることも可能です。
ここからは、住宅ローン控除の概要について見ていきましょう。
つまり、住宅ローンで支払った利息の一部が国から還付されるという制度のことです。
この住宅ローン控除制度を利用すれば、最大400万円以上の還付を受けることも可能です。
ここからは、住宅ローン控除の概要について見ていきましょう。
・控除率と控除期間
控除率は年末時点での住宅ローン残高の0.7%です。
また、控除期間は新築住宅が最大13年、既存住宅とリフォームが最大10年です。
新築住宅でも、適用される年度によって10年になる可能性がありますので注意が必要です。
また、控除期間は新築住宅が最大13年、既存住宅とリフォームが最大10年です。
新築住宅でも、適用される年度によって10年になる可能性がありますので注意が必要です。
・控除対象の課税所得
住宅ローン控除は、支払った税金の一部が返ってくるという制度。
その税金の種類とは、所得税と住民税(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内)の2つです。
まずは所得税分が還付対象になり、還付しきれない分が住民税から返ってくるという仕組みです。
その税金の種類とは、所得税と住民税(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内)の2つです。
まずは所得税分が還付対象になり、還付しきれない分が住民税から返ってくるという仕組みです。
・最大控除額
例えば、2023年中に長期優良住宅、または低炭素住宅を新築し入居した場合、13年間で最大455万円の控除が可能です。
また、一般住宅の場合は2023年中に新築して入居した場合、最大273万円の控除となります。
※住宅ローンの残高や支払った税金などにより、控除額が変わるのでご注意ください。
また、一般住宅の場合は2023年中に新築して入居した場合、最大273万円の控除となります。
※住宅ローンの残高や支払った税金などにより、控除額が変わるのでご注意ください。
・適用される住宅の要件
基本的には、下記の場合に適用されます。
・個人が住宅を新築する
・新築住宅を購入する
・一定の増改築が行われた住宅を取得する
・中古住宅を購入する
しかし、それぞれに条件があり、その条件を満たさなければ住宅ローン控除を利用することができません。
・個人が住宅を新築する
・新築住宅を購入する
・一定の増改築が行われた住宅を取得する
・中古住宅を購入する
しかし、それぞれに条件があり、その条件を満たさなければ住宅ローン控除を利用することができません。
住宅ローン控除の申告方法
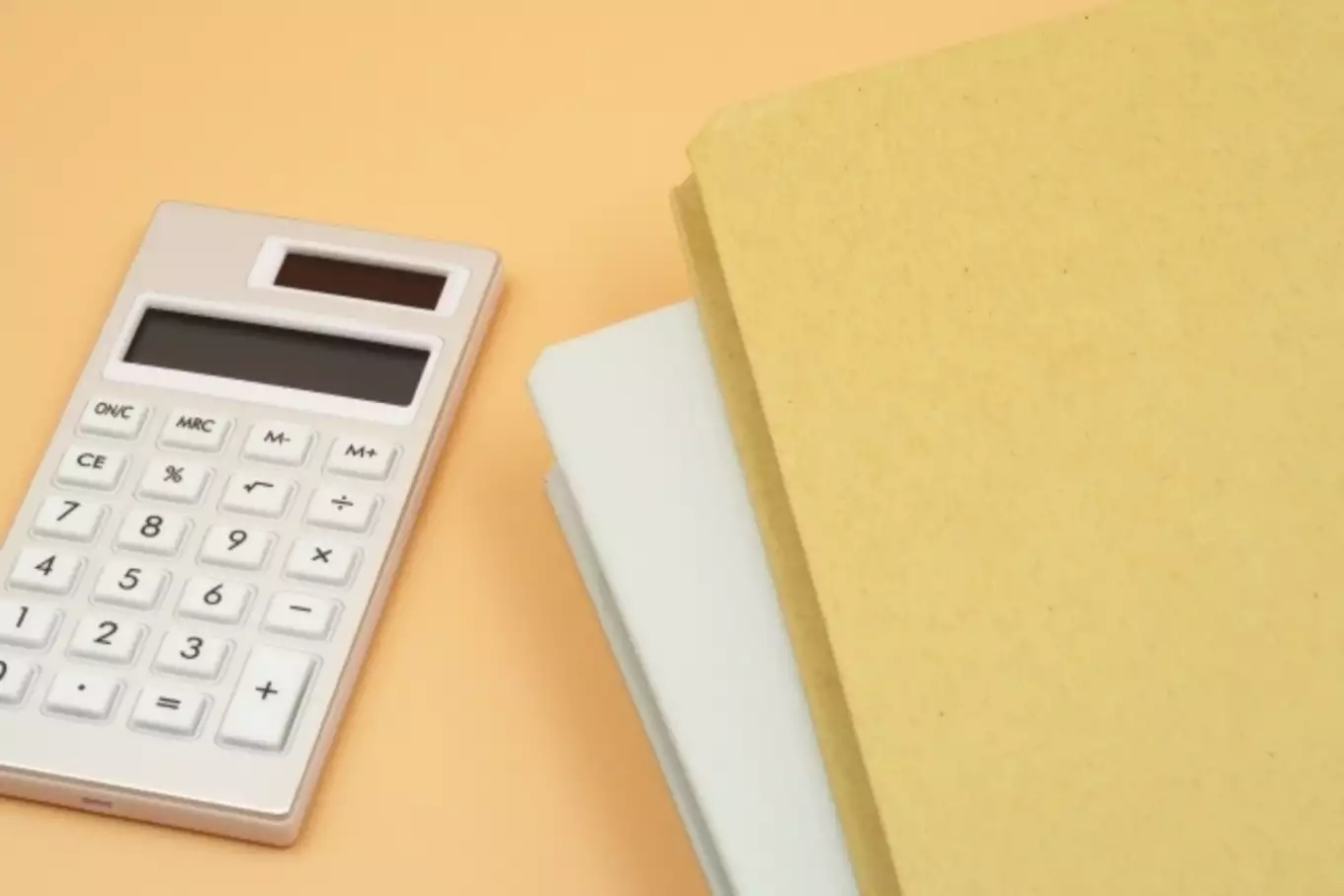
住宅ローン控除を受けるためには申告が必要です。
会社員の場合、初回のみ申告をすれば、その年以降は年末調整の対象になるので、自動的に控除されます。
※個人事業主などの年末調整を利用しない人は、2年目以降も確定申告が必要になるのでご注意ください。
ここからは、住宅ローン控除の方法について詳しく見ていきましょう。
会社員の場合、初回のみ申告をすれば、その年以降は年末調整の対象になるので、自動的に控除されます。
※個人事業主などの年末調整を利用しない人は、2年目以降も確定申告が必要になるのでご注意ください。
ここからは、住宅ローン控除の方法について詳しく見ていきましょう。
・申告期間
住宅ローン控除の申告は、確定申告の時期に行います。
※一般的に2月16日〜3月15日の期間です
※一般的に2月16日〜3月15日の期間です
・申告場所
申告する場所は大きく2つです。
・自宅でインターネット(e-tax)を利用して申告する方法
・税務署の窓口で申告する方法
詳細は下記の通りです。
1、国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告する。
2、税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申告する。
3、国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送する。
4、国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送する。
5、税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参する。
6、税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送する。
ただし、確定申告に慣れていない方は、確定申告書の作成方法や必要書類について税務署の窓口で相談に応じてもらえます。
少しでも不安がある場合は窓口で手続きするようにしましょう。
・自宅でインターネット(e-tax)を利用して申告する方法
・税務署の窓口で申告する方法
詳細は下記の通りです。
1、国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告する。
2、税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申告する。
3、国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送する。
4、国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送する。
5、税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参する。
6、税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送する。
ただし、確定申告に慣れていない方は、確定申告書の作成方法や必要書類について税務署の窓口で相談に応じてもらえます。
少しでも不安がある場合は窓口で手続きするようにしましょう。
住宅ローン控除の申告に必要な書類
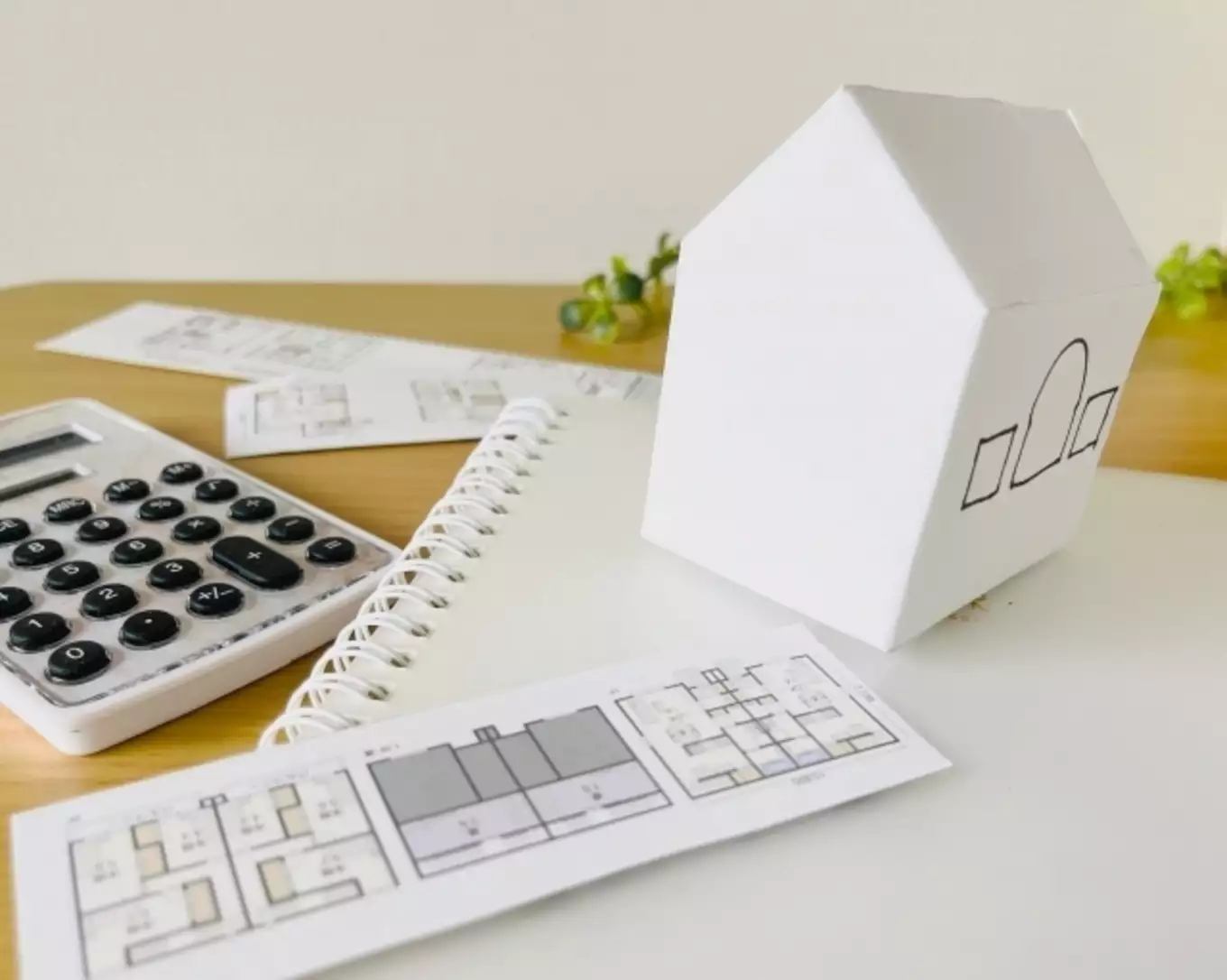
・確定申告書
必要項目を記載した確定申告書は必ず必要です。
国税庁のサイトから入手しましょう。
または、税務署でもらうことも可能です。
国税庁のサイトから入手しましょう。
または、税務署でもらうことも可能です。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
これは、住宅ローン控除の金額を計算するための書類です。
新築や中古、住宅の性能に関わらず必要ですので、全ての方が提出することになります。
この書類には住宅を取得した年月日、面積、価格、住宅ローンの残高などを記載します。
こちらも同じく、国税庁のサイトから入手しましょう。
または、税務署でもらうことも可能です。
新築や中古、住宅の性能に関わらず必要ですので、全ての方が提出することになります。
この書類には住宅を取得した年月日、面積、価格、住宅ローンの残高などを記載します。
こちらも同じく、国税庁のサイトから入手しましょう。
または、税務署でもらうことも可能です。
・本人確認書類
マイナンバーカード
または
マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票
+
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
または
マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票
+
運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
・建物、土地の登記事項証明書
建物、土地の登記事項証明書とは、法務局で取得できる登記簿謄本のことです。
不動産の所在や面積、所有者やその他の権利が記載されています。
法務局で取得、または司法書士事務所から送られてくる権利書に同封していることがあります。
この書類は原則提出が必要ですが、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載すれば、提出を省略することができます。
不動産の所在や面積、所有者やその他の権利が記載されています。
法務局で取得、または司法書士事務所から送られてくる権利書に同封していることがあります。
この書類は原則提出が必要ですが、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載すれば、提出を省略することができます。
・建物、土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
不動産会社で契約を締結した書類です。
どの不動産を誰から取得したのか、どの業者と建物の工事請負契約をしたのかが記載されている契約書のことです。
契約時に取得している書類です。
契約書類をまとめてあるファイルがあれば、その中を確認してみましょう。
どの不動産を誰から取得したのか、どの業者と建物の工事請負契約をしたのかが記載されている契約書のことです。
契約時に取得している書類です。
契約書類をまとめてあるファイルがあれば、その中を確認してみましょう。
・源泉徴収票
年末年始に勤務先からもらう書類です。
もし手元になければ勤務先に伝えて再発行してもらいます。
その場合は発行まで時間がかかることがありますので、早めに用意するようにしましょう。
もし手元になければ勤務先に伝えて再発行してもらいます。
その場合は発行まで時間がかかることがありますので、早めに用意するようにしましょう。
・住宅ローンの年末残高証明書
年末の時点で住宅ローンがどれだけ残っているかを記載した書類です。
住宅ローンの借入銀行から年末に送付されてきます。
もし無くしてしまった場合は、早めに銀行に連絡してください。
住宅ローンの借入銀行から年末に送付されてきます。
もし無くしてしまった場合は、早めに銀行に連絡してください。
・耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し、認定通知書の写し(条件を満たす場合)
不動産会社、または建築会社から入手しましょう。
住宅ローン控除で税金が返ってくる時期

税金の還付は、確定申告から約1ヶ月後に、指定した金融期間の口座に振り込まれます。
まとめ
今回は住宅ローン控除の基本的な仕組みと、申告方法、必要書類をお伝えしました。
住宅ローン控除を上手く活用すれば、大幅に税金が返ってくる可能性があります。
もし、住宅ローンを利用しての購入を検討されているのであれば、是非チェックしてみてください。
住宅ローン控除を上手く活用すれば、大幅に税金が返ってくる可能性があります。
もし、住宅ローンを利用しての購入を検討されているのであれば、是非チェックしてみてください。